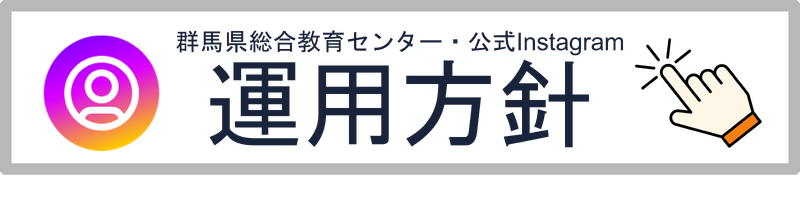|
〒372-0031 |
せん長の「ぽんぽこコラム」
「環境」と八百万の神
幼児期の教育で言う「環境」とは、なにを指すのでしょうか。それは、物だけではなく人、自然現象、空間、雰囲気等、様々な人、もの、ことが環境と捉えられています。その環境を保育者が(時には子供と一緒に)、子供の発達に必要な豊かな体験が得られるように意図的に関連させ、相互作用が生まれる状況を予測・期待して構成していきます。これが、「環境の構成」と言われる教育的行為です。
日本には、八百万の神がいると言われています。自然、人、道具、概念、気配等の中に、どこにでも神様がいるというアニミズム的な感覚です。これは、人間がものや自然等をどう理解するか、アフォーダンス理論を用いれば、そこから発せられる様々な情報の内、何をピックアップするかという考え方に至るのではないでしょうか。
「環境」と八百万の神、とても似ている気がします。環境の構成を行う際の思考として、環境の中にどんな意味を見いだすのかは、私たち保育者に委ねられています。ただ一人でそれを担うのは荷が重すぎます。子供たちの表情や言葉、行動、そして同僚保育者との会話から、多くの刺激を受けることで、たくさんの「八百万の神」と出会うことができるのではないでしょうか。
(中村 崇)
当番を生み出す
幼稚園での出来事です。
初めての給食の日、先生は大忙しです。
先生は、ご飯、味噌汁をよそい、おかずを盛り付けています。
先生「あー、忙しい、忙しい」
子供「先生、手伝おうか?」
先生「いいの、いいの。これは先生の仕事だからね。あー、忙しい」
子供は、ちょっと困り顔。
翌日、同じようにやっていると、また、
子供「手伝おうか?」
先生「いいよ、いいよ」
子供「やりたいんだよ。やらせてほしい」
先生「そう。では、エプロンとコックさんみたいな帽子を貸すね」
子供たち「えっ!、いいなぁ、私もやりたいなぁ」「私も」「私も」…
先生「こんなにたくさんの人がいたら、仕事にならないよ。困ったなぁ」
子供「順番にしたら。チームとかでさあ」
子供たち「いい考えだねぇ」
という過程を経て、当番が生み出されていきました。
手伝いではなく、私のやりたいことの一つとして。
子供「明日は給食当番だ、楽しみだな」 (中村 崇)
思考力の芽生えを養う保育
「幼稚園教育要領解説」には、自然と関わることの意味と指導の重点として「幼児期において自然のもつ意味は大きく、自然の大きさ、美しさ、不思議さなどに直接触れる体験を通して、幼児の心が安らぎ、豊かな感情、好奇心、思考力、表現力の基礎が培われることを踏まえ、幼児が自然との関わりを深めることができるよう工夫すること」と述べられている。ここでは、自然に直接関わる体験を通して得られる様々な能力の中で、特に思考力の芽生えに着目し、それを養うための保育の在り方を考えていく。
☆不思議さを感じる エピソード1(3歳児 10月)
昼食時、A児が天井で何かが動いているのを発見する。それは、メダカのいる睡蓮鉢の水に日光が反射して天井に映っているものだった。教師は、それが何かを答えるのではなく、この不思議な体験を大切にし、幼児から考えが出るのを待った。幼児は「やきいもみたい」「トイレみたい」「うみみたい」「ボクシングみたい」「くものすみたい」「もやもやしてるね」「へびみたい」と次々に言った。
思考力というと、今までの経験を新しい場面に適用したり、工夫したりするときに働く能力に目が行きがちである。しかし、試したり工夫したりする前に、関わる対象に心を動かし、好奇心や探究心を抱くことが重要である。エピソード1は、幼児が対象に不思議さを感じて好奇心をふくらませ、様々なものに見立てて遊んだ様子である。このように見立てて遊ぶことにつながる不思議さを意図的、計画的な環境の構成により体験をさせることには、難しさがある。しかし、幼児の表情や動き、言葉を敏感にキャッチして好奇心を抱く対象を捉え、その不思議さやおもしろさを十分感じて遊ぶような機会や時間を保障することが、思考力の芽生えを養うことに有効と考える。
☆概念を壊す エピソード2(4歳児 7月)
B児は、タライの水にビワの実を入れた。当然沈むと思っていたB児は、水に浮くビワを見て驚き「重いのに浮いてる」と呟いた。
その後、B児は牛乳パックでつくった船を浮かべ、石を乗せた。当然船は沈むだろうという予測の下に石を乗せたわけだが沈まない。次に両手に余るほどの大きな石を乗せた。それでも沈まない船に驚き、友達や教師にその事実を知らせた。興味をもった友達と、「この石ならどうかな」「二つ乗せても大丈夫かな」などと言い合いながら繰り返し試した。
教師は不思議さやおもしろさを感じて遊んでいるB児の心の動きを捉え、すぐに牛乳パックの船を準備した。そのことが、不思議さを追究しながら遊ぶことにつながった。幼児は自分の中にある概念に従い、結果を予測して遊ぶ。しかしエピソード2のように、自分のもつ概念が壊されるような体験をすると、驚きや不思議さを感じる。そして、その追究を通して、新たな概念を形成していく。自分のもつ概念が壊される体験を経て、新たな概念を構築していく中でも、思考力の芽生えは養われていくと考える。
☆考えを出し合い高め合う エピソード3(4歳児 7月)
教師は、幼児が噴水によってボールが押し上げられることなどに気付くことを期待して、スプリンクラーの回転部分を取り外し、噴水のように水が出る装置をつくった。
C児は、ミニパイロンやカラーボールを噴水の力で飛ばしはじめた。D児やE児も加わり、パイロンやボールを噴水の上に持っていき水の勢いを感じながら手を放す。ものが飛ぶときと飛ばないときの違いは何か、水量を上げて水の勢いを増せばよく飛ぶのではないかと、幼児同士のやりとりから考えが生まれた。そして蛇口のハンドルを回して水量を調節する役と、ものを飛ばす役に分かれて、「出し過ぎ。近づけないよ」「これじゃ全然飛ばないよ」などと声を掛け合っていた。そうした中、F児はペットボトルの口と噴水の口とを合わせ、手で押さえはじめた。ペットボトル内の空気が水かさが増すごとに圧縮され、F児が手を放すと1mくらい飛んだ。「ロケットだ」と幼児たちの歓声があがる。幼児たちは「小さいペットボトルの方が飛ぶんじゃない」とか「もっと水を出せばいいんじゃない」とか意見を交わしながら次々と試していった。すると、F児が持ってきたペットボトルの口が噴水の口径にぴったりと合ってはまった。教師は危険を感じ、近くにいる幼児にさがるよう声を掛けた。ペットボトルは水を噴射しながら5~6m上昇した。歓声が上がる。それ以降は、ペットボトルをセットし終えると、幼児同士で「危ないぞ、さがれ」などと声を掛け合ったり、手をつないで「1・2・3・4…」とカウントダウンではなくカウントアップがはじまったりして、一体感のある遊びに発展していった。
このように、幼児同士が目的を共有すると、新しい考え(遊び)が生み出される。中には、大人も驚くような遊びに発展するときもある。教師は、そのきっかけを確実に見取り、幼児同士が考えを出し合ったり、友達の考えを受け入れたりするよう援助していく必要がある。
自然に直接関わる体験を通して思考力の芽生えを養っていくには、幼児が次のような体験を積み重ねることができる環境の構成や援助を行っていくことが大切であると考える。
○不思議さやおもしろさを感じる事象に出会う
○自分のもつ概念が壊されるような体験を味わう
○共通の目的の実現に向かって考えを出し合う
(中村 崇)
本文は、中村 崇(2011)思考力の芽生えを養う保育.初等理科教育 2011年10月号 No569.農山漁村文化協会.の一部を加筆修正し掲載
幼児の運動発達を促す教師の役割
運動発達について、幼児の行動観察や幼児と関わる教師の在り方の考察から,明らかになったことは次のとおりである。
(1)情動が運動経過の変化に影響を与える可能性が示唆された。
(2)幼児の運動発達に関わる5つの特徴的な行動を見いだした。これは,幼児の運動を見取る教師の視点にもなり得ることが示唆された。
(3)上記の視点を活用する際の幼児と関わる教師の在り方は,教師自身の身体を通して敏感に幼児の内面を感知する姿勢をもつことであると言える。
以下に,明らかになったことがらを詳述する。
幼児の運動経過を見る視点として従来は,運動そのもの形態の変化を見たり,動作様式と比較したりする方法がとられていた。その重要性を認識しながらも,別の視点からの見方の可能性を探った。そこで着目したのは,運動が起こった背景やそのときの幼児の内面理解を通して運動経過を理解するというものである。特に幼児では,同じ運動でも,そのときの情況により運動形態に変化が見られる可能性があるからである(佐藤1))。
A児の行動観察からは,緊張や不安,喜びや嬉しさ,楽しさといった喜怒哀楽に伴う運動発生が見られた。すなわち情動が影響して発生する運動があることが分かった。
さらに,A児の行動観察で得た運動発達に関わる特徴的な行動に着目した。それは,①見る,②身体が一緒に動く,③模倣する,④運動感覚の類縁性(キネステーゼ・アナロゴン),⑤おもわずやってしまう動き,の5点である。
「見る」とは,他人の動きかたをよく観察して,まとまった動きのイメージを自分のなかに描く行為であると考えられる。「身体が一緒に動く」とは,その対象への運動共感の現れであり,別言すれば,対象となっている運動に引きずり込まれるような感覚を体感していると言えよう。「模倣する」ことについて,金子は,メルロ=ポンティの言葉を引き,「幼児は他者の動きの感じを運動メロディーとしてまるごと知覚し,しかもそれは対私的な運動認識ではなく,他者とともにある意識に基づいて共感する」2)からできることだと言っている。すなわち「模倣する」ことは,「見る」「身体が一緒に動く」と一連をなしており,対象になっている他者の内面を共有している感覚と言えるだろう。
「運動感覚の類縁性(キネステーゼ・アナロゴン)」とは,目的のために身体を動かした結果,目的とは全く違うこと,しかもできると思っていなかったことができる体験を通して説明されるものである。幼児は,遊びを他の目的のために行っているわけではなく,遊ぶこと自体に真剣に向き合っている。そのような幼児は,遊びのなかで,数多く「運動の類縁性」を体験しているだろうと考えられる。
「おもわずやってしまう動き」は,客観的に見ると,何の前触れもなく出現する動きである。これは,模倣により,ある程度とらえた運動の感じ(運動感覚)を実感してくると,気に入った動きや気になる動きになっていき,その動きの表出のことではないかと考える。これらの動きは,動きの洗練,成熟に向かっていく過程の行為なのではないかとも考えられる。
以上のように,幼児の運動をとらえる視点を得ることができた。ここで得た運動をとらえる視点を活用し,幼児の運動発達を促すためには,教師は幼児とどのように関わったらよいのか。その知見も本研究で得られた。頭での理解にとどまらず,教師自身の身体を通して敏感に幼児の内面を感知する姿勢,すなわち,幼児の身体の在り方を教師の身体が感知し,教師の身体の在り方が幼児の身体の在り方に影響を与えるという関わりである。
幼児の運動経過を見る視点として,運動が起こった背景やそのときの幼児の内面理解を通して運動経過を見るという視点からの分析を試みた。そこから分かったことは,緊張や不安,喜びや嬉しさ,楽しさといった喜怒哀楽に伴う運動発生,すなわち情動が影響して発生する運動があるのではないかということである。
さらに幼児の行動観察から,①見る,②身体が一緒に動く,③模倣する,④運動感覚の類縁性(キネステーゼ・アナロゴン),⑤おもわずやってしまう動き,という5点の特徴的な行動に着目した。これらは,他者の動きを目にするなど外部からの刺激が基になって自分の意識が働き発生する運動であると考えられる。そして,この5点の特徴的な行動は,幼児の運動発達をとらえる教師の観察の視点にもなり得ると考えられる。
以上の結果から,幼児の運動発達を促す教師の役割を整理すると次のように言える。
情動が影響して運動経過が変化することが示唆されたことから,不安や緊張感,精神的な圧迫からの解放,言い換えれば安心して遊べる,嬉しい・楽しい感情がわく環境の構成や働き掛けを行うことが,幼児本来の身体活動を保障し,運動発達を促すことにつながるのではないかと考える。
異年齢児と関わる状況の生成やモデルとしての教師の役割,対象にじっくり関わるための時間の保障,幼児の内面への共感などが,「見る」「身体が一緒に動く」「模倣する」などの幼児の姿につながると考えられる。また教師は,「運動感覚の類縁性(キネステーゼ・アナロゴン)」に関する動作を意識して見ることで,動作の獲得過程を幼児と共に感じることができると推測される。「おもわずやってしまう動き」を表面的にとらえず,一つ一つの動きや行為に意味を見いだし,尊重する姿勢で幼児に関わることも,運動発達を促す教師の役割であろう。
そして,遊ぶ幼児の身体の在り方を教師の身体が感知し,教師の身体の在り方が幼児の身体の在り方に影響を与えるという関係性を十分認識していく必要があろう。(中村 崇)
1)佐藤 徹(2014)運動発達査定における動感志向分析の意義,体育学研究59,pp.67-82
2)金子明友(2002)わざの伝承.明和出版:東京,p.408
本文は、中村 崇(2016)幼児の運動発達を促す教師の役割,群馬大学教育実践研究第33号,pp.227-235の一部を加筆修正し掲載
キネステーゼ・アナロゴン
「キネステーゼ・アナロゴン」??????って、はてな?がたくさん浮かびますよね。この言葉、何なのでしょう。キネステーゼとは、身体を動かすときの「コツ」や「感じ」などの運動感覚(「動感」と言う方が学術的には意味が近い)を表すフッサールによる造語です。アナロゴンとは、ある運動のもつ動きの仕組み(運動局面と運動リズム)にほとんど大きな違いがない類縁性をもつ、すでに習得している動きのことです。今回は、私の専門研究領域である運動発達における子供の動作習得やそれを支える保育者の在り方についてお伝えします。
運動ができるためには、これまでの運動経験をもとにして、「できそうな気がする」と思えるような具体的な動きの感じが必要です。そこで、今までに味わってきた運動感覚と、「今、子供が取り組んでいる運動」の感覚をつなぐ言葉掛けが重要になってくるのです。子供は今までに味わったことのある運動感覚と、これからやろうとする運動の感覚とが似ていることに気付けば、「あの感じでやれば、できそうだな」というある種の自信をもって運動に挑戦していくと考えられます。
例をあげます。足を地面につかないでブランコをこぎだす感じは、鉄棒の「足かけ振り」のキネステーゼ・アナロゴンと言えるでしょう。また、雑巾を絞る(縦絞り)動作は、棒を両手で縦に持って「グッ」と肘を伸ばして前へ突き出す(剣道みたいな)動作との類縁性があると考えられます。このようなことを念頭に置いて子供との生活を送ると、保育の新たなおもしろさが感じられるかもしれません。(中村 崇)
初出:ぐんしよう №204 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
「積み木を積んで家を作っているから、算数の図形につながっているよね」って、そういう理解でいいのかなあ?
小学校教師が、幼児教育施設における遊びについて教科内容を窓口に理解しようとするなら、そこで育っている「資質・能力」の本質的な理解には及ばず、入学してくる児童の「資質・能力」を小学校教育で生かすことは困難になるだろう。また幼児教育施設において保育者が、遊びについて小学校の教科内容の類似点に着目するならば、豊かで深い多義的な体験を支えることは困難になるだろう。
子供が遊ぶ、その行為のなかに、小学校以降の教科教育の内容(すること)との類似性、関連性を見て、つながっているか否かと言っていることに何の意味があるのだろうか。遊ぶということを、人間の生きるという意味での総合的な行為のなかにあると考えれば、学校教育の教科内容とつながっているに決まっているのだから。日本で言えば学校、教科教育の歴史はおよそ150年、寺子屋等を考慮しても数百年の歴史である。私たちホモ・サピエンス(現生人類)は、40〜25万年も前から遊び、そして生活してきた。約1万6000年前から生活している縄文の人たちは、仲間との共通理解の中で長さの単位をもち活用していた。そのように、生活の中で共有した方が生きやすいと思われる文化的な要素を、関連事項として取り出し体系的に整理したものが、教科である。すなわち、子供が遊ぶなかで経験されることが、教科内容につながっているということは容易に理解できる。
学校教育の教科内容はあらかじめあるわけで、そこへの子供の興味・関心、関わる意欲をどのように支えるか、どのように湧き立たせるかが教師の役割として重要なのではないだろうか。教科の窓口では、人間は理解できない。子供理解の上に、教科内容に子供が自ら向かっていく方法を探るのが教師の役割であろう。人間を理解しなければ、教科は成立しないのは当たり前である。教科の窓口で子供の行為を理解することから脱却しなければ、自由進度学習や個別最適な学び、主体的・対話的で深い学びなど実現するはずがない。
「遊びの人類学ことはじめ フィールドで出会った〈子ども〉たち」(2009 昭和堂)の中で文化人類学者 亀井伸孝は、「ヒトはなぜ遊ぶのか。それは楽しいからだという答えに行き着くかもしれない。であるとするならば、ヒトはなぜそのようなことがらを楽しむ能力をもって生まれるのか。それはおそらく、自然環境のなかで狩猟採集文化が無理なく伝承されていくための、不可欠かつ有用な能力の数かずであるのだろう。自然界における進化のプロセスで、そのような性質がいつしかそなわっていったのは興味深いことである。私たちヒトの社会がどこまで文化変容をとげたとしても、遊ばずにはいられない生き物であり続けていることは明らかである。それは、文化が変わっても変わることのないヒトの本性であり、狩猟採集民としてこの世に出現したヒトのルーツに直接関わっていることにちがいないのである」と述べている。すなわち、この遊びが、どの教科につながっているとか分析しても意味がない。つながっているに決まっているのだから。生きる「人」としての育ちに目を向け、場(関係性を含む)が変わっても、子供がその育ち(資質・能力)を生き生きと発揮するような状況づくりが大切なのである。そのために、架け橋期の教育について、幼児教育の保育者と小学校の教師が、相互理解を深め、協力することが求められているのである。子供を中心に考えたときに。(中村 崇)
クリティカル・シンキングのすゝめ
みなさんは、「体育座り(三角座り)」について、何か思うところはありますか。深く考えたことはないけれど、体育館・遊戯室等に集合したときや体育・運動会のときの「正しい」座り方だよね、と思っていますか。私は、大いに言いたいことがあります。みなさんは、子供たちへの願いとして、自分の考えを生き生きと表現し、友達の意見を傾聴して刺激し合いながら学んでほしいと思っていらっしゃるのではないでしょうか。しかし、「体育座り」の姿勢は胸を閉じるようになり、自己を発揮する姿勢とは真逆です。姿勢の状態が心の在り方に重要な影響を与えることを示唆している研究もあります。「体育座り」の姿勢は、心理的に「閉じている」ことを表す姿勢です。この姿勢が、いつから教育現場で活用しはじめられたのかを調べると、1965年に当時の文部省が「集団行動指導の手びき」で「腰をおろして休む姿勢」として紹介したことがきっかけでした。一例なのです。しかし、保育者・教師側から見ると子供の管理がしやすい姿勢と認識されたので全国的に活用されたと思いますが、子供側から見たときには自由感を感じにくく自己発揮しづらい姿勢と言えるのではないでしょうか。現在、腰への負担や内臓の発達への負の影響が医学的な立場から懸念されています。
しかし、今回本当に言いたいのは前述の事柄ではありません。実は、「体育座り」にまつわる話に似たような現象が、今、「架け橋期のカリキュラム」においても起きつつあるのではないかと心配しているのです。文部科学省が公開している「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き(初版)」の「3-(2)開発会議で開発する架け橋期のカリキュラムのイメージ」に、私の心配の発端があります。この「架け橋期のカリキュラムのイメージ」には、致命的な弱点があると感じています。まず一見、一枚紙にまとめなくてはいけないような印象を与えています。さらに、「園で展開される活動/小学校の生活科を中心とした各教科等の単元構成等」の欄があり、○○遊びと記入したくなったり、単元名の羅列になったりする可能性が強いのです。そのような記述をしても、何の意味もありません。幼児教育の指導計画や週・日案の「内容」の部分が大事なはずです。すなわち、活動名・遊びの名称・単元名ではなく、発達を念頭にそこで経験させたいことを明記することが意味あることではないかと思うのです。経験させたいこととは、学校生活や教科教育の基盤となり、そこでの発揮が期待される資質・能力≒非認知能力と考えます。しかし、幼児教育施設の指導計画等を見ると、いまだに内容として「○○遊び」と記入している園が多いことを考えると抜本的な改革が必要なように感じます。文部科学省の上述の資料の解説をじっくり読めば、単に活動や単元名の羅列をするものではないことは分かるのですが、例示された表のインパクトが強くて、一般的には理解が深まっていないように感じます。また、ここで作成した「架け橋期のカリキュラム」と、従来の指導計画とで、二重の計画ができてしまう中で、それをどう活用するというのでしょうか、という疑問も浮かびます。私は、文科省が示したのは一例だよ、と大きな声で言いたいのです。
そこで着目していただきたいのは、群馬県総合教育センター幼児教育センターの開発した「ぐんま架け橋プラグラム」です。上述の懸案事項を乗り越える提案と自負しています。Webページにて公開していますので、ぜひご活用ください、また、保育アドバイザー派遣事業にて、「ぐんま架け橋プラグラム」の活用に向けての研修も提供しています。(中村 崇)
幼少年期のスポーツに対する子供の意欲と親の期待について③
30数年前、学生だったときに書いた論文を読み返してみました。当時の私が課題だと思っていた事柄は、子供を主語にする教育論、伴走者としての教師の在り方、非認知能力の重要性等が教育的課題として認識される社会の潮流により好転している部分もあれば、未だ課題のままの点もあるなという感想です。
22歳の私が書いた論文の一部を3回に分けて掲載します。本文はその3回目です。言葉や表現等、文言の調整は行いました。
指導者に望むことは、技術を伝えることばかりにとらわれてはいけないということである。技術を伝えることは指導者の役割であるが、指導者の第一の役割は、子供たちにスポーツの楽しさを伝えることであると考える。そして、自由にスポーツ活動が行えるように安全面に配慮し、環境の整備を行っていくことが大切なのではないか。
実際の指導場面でも、気を付けなければならないことがある。それは、指導者が何気なく言った言葉が、子供の心を深く傷つけてしまうことがあるということである。子供の心をより深く理解するための努力が望まれる。嫌々やっているのであれば、やめたほうがよいと思う。子供は敏感であるから、大人のそのような心はすぐに読み取るだろう。指導者が、子供に及ぼす影響は大きい。そのことをよく踏まえて行動し、指導的立場に立つ必要があるだろう。
もう一つ、気を付けなければならないことがある。それは、勝利至上主義的指導にならないようにすることである。知らず知らずのうちに勝つことだけをめざして、子供のためのスポーツのはずが、指導者の勝ちたいという欲求を子供を使って満たそうとする状況に陥ることがある。子供のスポーツは、大人のスポーツとは違うのである。大人のスポーツの縮小を子供のスポーツと考えている人がいるが、その考えは明らかに間違いである。大人と子供の体は全く違うものと考えなければならない。子供の発達に合わせ、競技方法も変えて考えていかなければならない。サッカーのゲームで言えば、幼児期は柔らかく軽いボールを使用し、ゴールへの蹴り合いが主となるゲームがよい。柔らかくて軽いボールを使用するのは、足の障害を予防することと、ボールは怖いものではないということを伝えるためである。空気を少し抜いて弾みをおさえることも有効である。なぜなら、ボール・コントロールがしやすくなるからである。少年期前半(小学校1~3年生くらい)では、ボールは3号球を使用し(規定では小学生の使用球は4号球)、コートも小さくして行う。ボールの空気を少し抜くことも継続してよいだろう。ゴールキーパーは置かず、オフサイド・ルールも採用しない。扱いやすい小さなボールを使用し、オフサイドのような難しいルールをなくすことにより、自由なプレーが身に付くと考える。そしてゴールキーパーがいないことで点が多く入り、おもしろさが増すだろう。少年期後半(小学校4~6年生くらい)では、ドリブルなどの個人技を重視し、ロングキックや強いキックを望む必要はない。これらは私の考えであるから、様々な意見があるだろう。しかし私が言いたいのは、子供一人一人の発達を考え、その子供に合った指導を望むということなのである。
大人と同じような質・量のスポーツを行うことは、幼児期・少年期でのチャンピオンを養成するのには適しているであろう。しかし、小さなチャンピオンを作ったとしても、その子供は少年期で全てをやり終えたように感じ、「あれだけ苦しいことに耐え、頑張ったのだからスポーツはもういい」という気持ちになりかねない。これが燃えつき現象(バーンアウト)と言われていることであるが、このような子供を出さないように、指導者は指導方法を考えていかなければならないと考える。
子供のスポーツに関わる全ての大人たちには、子供のスポーツを遊びと捉え、スポーツの楽しさを伝えることに重点を置くことが望まれる。そして、子供の意欲が、大人によって消されることがないように望んでいる。(中村 崇)
本文は、中村 崇(1992)幼少年期のスポーツに対する子どもの意欲と親の期待について.上越教育大学.pp.63-66の一部を加筆修正し掲載
幼少年期のスポーツに対する子供の意欲と親の期待について②
30数年前、学生だったときに書いた論文を読み返してみました。当時の私が課題だと思っていた事柄は、子供を主語にする教育論、伴走者としての教師の在り方、非認知能力の重要性等が教育的課題として認識される社会の潮流により好転している部分もあれば、未だ課題のままの点もあるなという感想です。
22歳の私が書いた論文の一部を3回に分けて掲載します。本文はその2回目です。言葉や表現等、文言の調整は行いました。
親に望むことは、子供にプレッシャーを与えないようにすることである。他の子供と比べたり、試合などで勝つことを強く望んだり、過度な応援をしたりすることなどは、子供の心に大きなプレッシャーを与えることになる。本来のプレーが歪めらる可能性もある。さらに、子供がスポーツを楽しむことを妨げるとも考えられる。もっと自由に、大きな心で見守ってほしい。そして、時には一緒にスポーツを楽しむことも大切ではないだろうか。今までとは違った子供の表情を見ることができるのかもしれない。
スポーツ指導に名を借りて指導者にしつけを望む親がいる。これは見当違いである。指導者も道徳的に反する行動には厳しく対応する必要はあるだろうが、練習や試合の指導を通して根性を付けてもらいたいとか、厳しく指導し忍耐力を付けてほしいといったことを望む親がいる。根性、忍耐力といったものが、もしスポーツで養うことができるのであれば、それは子供が自分自身でその力を発見し、育てていくものだと考える。他人により強要されて付けた力など、本質的な力ではないだろう。人間として成長する中で様々な経験をし、様々な状況に立たされたときに、自分でそれを乗り越えていく上でそれらの力が育てられ、発揮されていくのだろう。親はもっと子供の自由な活動を認め、成長を待ち、そして見守っていくことが必要であり大切なのだろう。(中村 崇)
本文は、中村 崇(1992)幼少年期のスポーツに対する子どもの意欲と親の期待について.上越教育大学.pp.63-66の一部を加筆修正し掲載
幼少年期のスポーツに対する子供の意欲と親の期待について①
30数年前、学生だったときに書いた論文を読み返してみました。当時の私が課題だと思っていた事柄は、子供を主語にする教育論、伴走者としての教師の在り方、非認知能力の重要性等が教育的課題として認識される社会の潮流により好転している部分もあれば、未だ課題のままの点もあるなという感想です。
22歳の私が書いた論文の一部を3回に分けて掲載します。本文はその1回目です。言葉や表現等、文言の調整は行いました。
子供が自主的にスポーツをはじめようとする要因の中に、あこがれの選手の存在がある。他の要因としても、そのきっかけが保護者や兄姉であったり、学校や幼稚園等の教師の影響であったり、アニメやCMであったりもするだろう。このように考えると、根底にあるものは「あこがれ」があると言えるのではないか。換言すれば、視覚的・聴覚的刺激を手掛かりにイメージを形成する。それにより興味が起こり、意欲へと移っていく。その意欲が環境を媒介に動機づけられ、行動へと子供を導く。その興味が向けられたものがスポーツであれば、スポーツ的な遊びへと発展していくであろう。
事例を挙げる。幼稚園教育実習中の出来事である。“お楽しみ会”のときに私がサッカーのユニフォームを着て、頭や腿、肩、足の甲などを使ってのボールつき(ボールリフティング)を子供たちの前でやってみた。すると翌週(“お楽しみ会”は土曜日だった)には、子供の中からサッカー的な遊びが出てきた。遊戯室の対面の壁をゴールと見立てての簡単なゲームではあったが、子供たちの顔は喜びに満ちていた。そして約一ヶ月後の作品展では、サッカーをしているところの紙版画を作った子供が二人いた。
本来、子供のスポーツとは、遊びとしての活動であるべきだろう。しかし現代では社会構造の変化に伴い、遊びとしてのスポーツが発生する広場や空き地が減少し、その代役として組織的なスポーツクラブが求められている。この現象は、現状から考えれば仕方ないと考えられるが、その中で大切なのは、大人、特に子供の親と指導者が、子供のことをどのくらい理解しスポーツ活動に関わっていくかということであろう。(中村 崇)
本文は、中村 崇(1992)幼少年期のスポーツに対する子どもの意欲と親の期待について.上越教育大学.pp.63-66の一部を加筆修正し掲載
てんぷら
葉っぱのてんぷらレシピを記します。
これは、以前お世話になった保育者の方から教えていただいたものです。
材 料:新鮮な葉(雑草の大きめな葉)・水・おがくず
作り方:①葉を水につけて、濡らします。
②濡らした葉におがくずをまぶします。
③皿に盛りつけます。
園におがくずは常時ないですよね。子供たちと一緒に遊ぶ中で、おがくずの代わりに使ってみたものは、栗の花や枯れた葉をすり鉢で細かくしたものです。
子供たちと「代替食材」を探すのもおもしろいでしょうね。(中村 崇)
「の」の ひみつ
Googleマップを見ていたら、?!!「の」があるではないですか。おもしろい、なんだろう、という思いに駆られ調べてみました。あるお宅の庭にある道でした。この心が躍る体験は、貴重な「溶解体験」(以前このコラムに書きました)になりました。
今回は、「の」のひみつを探っていきたいと思います。なんの「の」かと言いますと、「発達段階」と「発達の段階」、「発達課題」と「発達の課題」、「環境構成」と「環境の構成」の「の」です。「の」が付くか否かで、それぞれが表す文言に違いはあるのでしょうか。
「の」が付くときは、例えば「環境」と「構成」を分けて捉えてほしいときなのだと考えます。すなわち、「発達段階」、「発達課題」、「環境構成」が従来もっている意味とは違う意味を表現したいのだろうと考えます。
「発達段階」とは、多くの人に共通して見られる発達の道筋であると言われています。一方、「発達の段階」とは、人生という道の過程での変容としての「発達」における、その人またはその人たちの今の位置という意味での「段階」と考えられます。
「発達課題」とは、人間が健全で幸福な発達をとげるために各発達段階で達成しておかなければならない課題であり、次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題があると言われています。一方、「発達の課題」とは、「発達」という人の生きる過程の中で、その人が乗り越えることで新しい世界が開ける意味での「課題」と考えられます。
「環境構成」とは、保育者が望んでいる遊びや活動を引き出すための材料や用具を用意し子供の活動を誘発するという考え方を基にした物的環境を準備・配置することと言われています。一方、「環境の構成」とは、子供の興味・関心に即した「環境」(もの、人、自然・社会現象、時間、空間、雰囲気など)を相互に関連させながら、その子供にとって必要な体験を積み重ねていける状況づくりを「構成」と捉え理解することができます。
「の」のひみつを探る話はこれでおしまいです。様々な考え方はありますが、私なりの考えをまとめてみました。この思考過程は、私にとっておもしろくて刺激的な体験でした。(中村 崇)
Googleマップは、Google LLCの商標です。
初出:ぐんしよう №203 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
ところでさぁ
幼稚園で担任をしていたときの話です。
Aちゃんが、おうちの方の仕事について、自分が知っている情報を情熱的に伝えています。
A:「印刷の仕事はねえ、大きな機械を動かしてね、すごいたいへんなんだよ」
私:「そうなんだぁ。たいへんな仕事なんだね」
A:「そうなんだよ」
Aちゃんの動きが一瞬止まり、そして私の顔をじっと見つめて
A:「ところでさぁ、せんせいって、何の仕事してるん?」
私:「えっ?‼」(今度は私の動きが止まった)
保育者として、Aちゃんからもらった最高の言葉だったと思います。なぜなら、毎日、真剣に子供たちと遊んでいたことを認められたと思うからです。Aちゃんは、この「せんせい」という大人は毎日、自分たちと遊んでいて仕事をしているのかなあ、不思議だなあ、と思ったのではないでしょうか。
子供の言葉を大人の視座で理解(理解力の不足など)するなら、子供の心に寄り添う教育の実現は難しいと考えます。そして子供の姿は、保育者の保育についての評価であると考えます。子供の評価のみで、保育者自身の評価が外れていることはないでしょうか。(中村 崇)
ゴム跳び?
ある園の園内研修に伺いました。幼児の運動発達について、実技を交えながらの研修です。私は先生方に問い掛けます。「子供のころ、ゴム跳び、したことありますか?」
「あります。あります」(少数派)
「えー?ないです」(多数派)
あります、ありますの二人の先生にお手伝いいただいて、私がまずはやってみます。地域ごとにやり方は様々だと思うので、「○○町で生まれ育った、○○歳の私が子供のときにやったのは」と言いながら、「グー・パー・グー・踏み・グー・パー・ねじって・ピョン・A・B・C」と跳んでみます。
「おー‼」(拍手)と先生方が盛り上げてくれます。
続いて、あります、ありますの先生がノリよく、「○○市の○○歳がやりまーす」と言って、私とはちょっと違ったやり方を見せてくれました。
「おー‼」(拍手)と先生方が笑顔になります。
少数派は保育経験を重ねた先生方で、多数派はこれから保育者としての経験を積み重ねていこうとする先生方でした。このように自分の子供時代に遊んだことなどを実際の動きとともに伝え合う機会は、相互理解を促し、同僚性を高めることにつながるでしょう。
また、自身の幼少期の記憶をたどってみると、子供にとって遊ぶこととは何かについて、じっくり考えるきっかけになるのではないでしょうか。(中村 崇)
駄菓子屋のおばちゃん方式
子供のころ、「おぎんちゃんち」という駄菓子屋さんに仲間と一緒によく集まっていました。店主のおぎんちゃんは、子供たちをよく理解していたように思います。今で言うインフルエンサー的な子に、「今度、学校でビー玉、流行らせておくれ」と言って、ビー玉が数個入っている袋を無償(ただ)で渡すのです。ビー玉をもらったその子は、仲間にビー玉で遊ぼうと誘い、瞬く間にビー玉が流行り、「おぎんちゃんち」の売り上げは伸びることになります。
私は教師・保育者になってから、この現象を思い出し、人の行動変容に係る環境(人的なものを含める)の重要さに気付いたのでした。それ以降、私はこれを「駄菓子屋のおばちゃん方式」と呼んでいます。(中村 崇)
「環境の構成」と「方法としての教師」
「環境の構成」とは、子供が興味・関心のある環境に働き掛けて遊ぶことで、(子供本人は期せずして結果的にもしくは近い将来に)自身の発達の課題を自分で乗り越えるための意味のある状況づくりをする教師の営みであると私は解釈しています。すなわち、ものを配置するだけにとどまらず、時間や雰囲気等が相互に関連し、周囲の人(友達・教師など)との関係性の中で環境が意味(教育的価値)をもつことに教師は意識を向ける必要があるということです。さらに、遊びの展開により環境は再構成され、常に動的な遊びを支える役割も忘れてはなりません。教師が望んでいる活動を引き出すための材料や用具を用意し、幼児の活動を誘発する“コーナー保育”に代表される「環境構成」とは明らかに違うものなのです。子供がエージェンシーを発揮し、自らの世界を広げていくためには、「環境の構成」の考え方が必要になってきます。
環境の構成が有効に機能するためには、教師の在り方が重要になってくると考えます。我々幼児教育センターでは、子供が環境を通して自ら主体的に学んでいくために欠かせない存在である教師を「方法としての教師」1)2)と呼ぶことにしました。「方法としての教師」とは、子供がねらいに向かうための手立てとしての教師の在り方であり、教育の手段としての教師の存在とも言えます。いくら物的環境を整えても、それらと子供を結びつける意図的な教師の動きが不可欠であり、具体的には「子供の活動の意味を理解する」「子供の目線に立つ」「思いに共感し共鳴する」「学ぶ姿や関わる姿のモデルになる」「必要な人に対して必要なときに必要な援助を行う」「子供が精神的に安定するためのよりどころ」などの役割が重要であると考えます。このような教師の存在により子供は、「安心」と「自由感」を得て主体性を発揮していくでしょう。
かねてより研修等でお伝えしてきたことですが、「○○遊び」をさせることが重要なのではなく、子供がどのようなことをして遊んでいても、その中に教師が教育的価値を見いだすことが重要なのです。これが環境を通して行う教育であり、遊びを通した総合的な学びなのです。
「環境の構成」は、小学校以降の教育でも有効に働くと考えます。(中村 崇)
1)中村 崇(2016)幼児の運動発達を促す教師の役割.群馬大学教育実践研究 第33号 pp.227-235
2)大島 崇・中村 崇・太田紀子(2025)子供に内在する非認知能力の発揮及び伸長を促す架け橋期の教育.群馬県総合教育センター
参考資料:森上史朗・柏女霊峰編(2011)保育用語辞典[第6版].ミネルヴァ書房:京都.
初出:ぐんしよう №202 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
一部を改稿して掲載
顔がぬれて ちからがでない
Aちゃんは、担任している私にたくさん話をします。しかし、どうもおとな(私)に頼りがちな気がします。
「ねえ、せんせい。これつくって」(折り紙の本をもってきて)
「せんせい。トンネル掘って」(砂場で山を作っていたとき)
ある日、私はAちゃんの「ねえ、せんせい。ウサギの部屋作って」に対して、「顔がぬれて、ちからがでない」と応答しました。Aちゃんは、「アンパンマンかぁ~‼」(笑)・(#怒)と、にやけながら怒り口調で言葉を返し、自分でウサギの部屋を作り始めました。私は、少したってから「私にお手伝いできることはありますか?」とAちゃんに言葉を掛けると、Aちゃんは「じゃあ、ここおさえといて」と言いました。
Aちゃんの遊び(生活)について、Aちゃんが主体になった瞬間でした。(中村 崇)
新しい感覚を味わう
ビニールプールからあふれ出た水が、園庭を流れていく。私は、乾季の大地に突如押し寄せるように静かだがあたかも命が宿ったような水の流れに心動かされ、「おもしろいなぁ」との思いで見ていた。誰かと共有したくて、近くを通りかかった3歳児のA児に「あっ」と言い、指をさしながら注意を向けた。
これがA児との出会いである。
A児は、乾いた地面を進む水を見て、そして私の顔を見たかと思うと、急いで砂場へ走って行き、タライに汲んである水をコップですくい再び私のところに戻ってきた。乾いた地面を進む水の最先端に、そのコップの水を注いだ。そして私の顔を見て「ニヤリ」とした。私が「おう」と声を上げながら、「そうそう、この進む水、おもしろいよね」という思いで笑顔を返すと、もう一度砂場から水を持ってきて同じようにした。
その後A児は砂場で、既に誰かによって作られていた山の周りに溝を掘り水を流すことを30分以上続けた。A児なりに、様々な試みをしているように見えた。その間、時折、近くにいる私の顔を見たり、笑顔を向けたり、持っている道具を見せたりしていた。私も、目を大きくしたり、「わあ」と感嘆の声を上げたりしながら応答していた。
園庭南側にある3m弱の樹木間には、2本のロープがピンと張ってある。1本は地上30cmくらいのところに、そしてもう一本は地上1mくらいのところに張ってある。まるで弾力性のある鉄棒のようだ。
裸足のA児はI先生の手を引き、この2本のロープのところまで招いた。
「見ててね」という表情で下のロープに乗り、上のロープを片逆手(右が逆手・左が順手)で鉄棒のように握った。右から片足ずつ上のロープに裸足の指を掛け、「蹴上がり」に向かう過程の体を「く」の字に曲げ足先を鉄棒に近づけるような姿勢を数秒間、維持した。
見ていたI先生は、「すごい、すごい技、さっきとちょっと違ったねえ」と称えた。I先生は「A児と同じ」という思いからだろうか、A児の顔を見ながら片足を上げて伸ばし、「サルみたい」と伝える。A児の表情が更に緩み、白い歯を見せながら、もう一度する。今度は右足はロープに掛かったが、左足はうまく掛からず、地面へ着地する。
A児が振り返るとI先生は他の幼児に関わっていて見ていないことに気付く。すぐにI先生のところに行き、他の幼児が持っている虫かごをI先生に促されながら覗くが、手はI先生の腕を取り、自分のところに再び来るよう促す動きをする。しかし、虫が小さいという話題になり、A児も話を合わせて両手をパチパチ打ちながら「ちっちゃいねぇ、あおむし」と言い、近くにいる私の顔を見る。そして、再びロープに戻るも、振り返り、「もうちょっと、このぐらいだった」とI先生と他の幼児の会話に呼応するように左手で小さい虫を表現し、更にI先生の応答を受けながら下のロープに乗り再び「『く』の字の姿勢」をとる。しっかり両足が掛かった状態で、身体が2往復、揺れる。「すごい、ブラブラだ」「さっきと、また違ったね」とI先生が言葉を掛ける。
B児がA児の右隣にやってきて下のロープに乗り、上のロープを首の後ろで担ぐようにして順手で握る。そして、横目でA児のすることを見る。
A児は、今度は逆手でロープを握り、「『く』の字の姿勢」に臨む。右足の指はしっかりロープに掛かるが、左足がうまく掛からず、しかし左足を下げずに高い位置をキープしながらなんとか引っ掛けようとする。身体は先程のように揺れている。前へ揺れるときに、左足をロープに掛けようとする。左足は左手の外側(左側)にいき、一瞬ロープに左足が触れ地面に下りる。
I先生が、二人がロープに乗っているのを見て、「AちゃんとBちゃん(二人とも同じ名前:○○ちゃん)、二人○○ちゃん」とその様子を他の幼児に伝えている。
B児もA児と同じようにしようと試みる。B児は順手で、左足をまずロープに掛けようとするが、うまくいかず、ぶら下がった状態になりつつ膝を上げて地面に足がつかない姿勢を少し揺れながらキープする。
A児は、ロープにぶら下がっているB児を見て、「よし、やるぞ」という感じで、逆手でチャレンジするがうまくいかず、地面に下りる。もう一度チャレンジすると、今度は右足がしっかりロープに掛かり、続いて左足も掛け、身体が揺れながら姿勢をキープする。
B児はそれを横目で見た瞬間、ロープから下りて、靴を脱ぎ、靴下を脱いで裸足になる。
私は、二人の姿を背後から見ていたが、ここで二人の正面に移動した。するとA児は地面に立ちながら、上のロープを逆手で握り、私の顔を見ながら歯を食いしばって強く引いたり押したりを繰り返す。横にいるI先生の顔も見る。そして、下のロープに乗り、挑戦する。左足が掛からないうちに右足に力が入ったままロープから外れて、勢いよくまるで鉄棒技「グライダー」の着地のようになる。びっくりした表情でI先生を見てから私を見る。そしてすぐにまた挑戦する。右足が掛からず、ゆっくり着地して、すぐにI先生を見る。
裸足になったB児はロープに戻って、チャレンジすると「『く』の字の姿勢」ができた。それを見ていたI先生は「できた、できた、Aちゃんと同じ、足も同じ」と言葉を掛ける。
その時、C児がI先生の傍らに来たが、A児がロープを握っている位置にも非常に近く、その圧からか、A児はうまくロープを捉えられず手が離れ、下のロープから落ちた。慌てて下のロープに跳び乗り、ロープを握り直すと、順手になった。その握りのまま、「『く』の字の姿勢」に臨み、成功する。しかし今までのA児の姿と少し違う。肩が後方に傾き、首も後方へ投げ出され、後ろの景色が見えるような状況で、力みがなく、リラックスしているように見える。A児は地面に下りた後、満足げに手をポンポンと叩き、再びチャレンジする。まず揺れているロープを片逆手で安定させるように握り、その後順手に持ち替えて、「『く』の字の姿勢」を成功させた。快さを感じているような清々しい表情であった。
- A児との出会いの情況、砂場でA児を見守る私の姿勢(構えといってもよい)により、かなり短時間にA児と信頼と呼べる関係が構築された。
- 私の応答は、言葉のやり取りよりも、「おもしろい‼」「不思議‼」という感覚が振動しあって伝わり合っていくという関わり。
- 深い信頼関係にあるI先生を支えに、そして「先程会ったばかりだけど自分をよく見ていて、おもしろがっているおじさん」の私を支えに、A児は砂場での長時間に及ぶ様々な試み、ロープに関わっての試行錯誤を行っている。
- 先生の言葉「さっきとちょっと違ったねえ」「すごい、ブラブラだ」「さっきと、また違ったね」等は、前の自分との比較、身体の状況を表し、A児に自身の運動の経過を意識化させている。また、「AちゃんとBちゃん(二人とも同じ名前:○○ちゃん)、二人○○ちゃん」は、他者(B児)の存在を顕在化させている。
- 片逆手だと揺れているロープを安定させられること、逆手だと足を掛けるロープに集中できること、そして逆手だと肩から首にかけても強く力が掛かり、それが身体全体にも影響を及ぼすこと、順手だと肩や首の力が抜け、肩から首が下へ向くので両足が上がりやすいこと、などを感覚として味わったのだろうか?
- ロープに関わっていくときに、最初は「先生に見てほしい」から中盤では「B児を意識して」、最後は「『く』の字の姿勢」の快さを感じて、というふうに内面に変化が起きているのではないか。 保育者がおもしろがって見ていてくれるという安心感(信頼関係)があると、子供は自ら挑戦していく。見ていてくれる保育者を踏み台(足場)にして、自分のやりたい世界に進んでいく。
- 困ったときにいつも助けてくれる先生ももちろん大切だが、「おもしろい世界を一緒に見て共感する」ことの中で、信頼関係を築いていくことも大切。
- 私は「誰かと共有したくて」と表現した。大人からも発信する。「先生が感じているおもしろい世界を一緒に見て‼」という思いである。今、もしかしたら足りないかと思う保育者の働き掛けが、ここにあるように思う。絵本を選ぶときも、遊びを創っていくときも、世の中にはこんなおもしろい世界があるんだよと、子供と共有したくて「もの」を出したり、言葉を掛けたりしても、時にはよいのではないか。(中村 崇)
幼児の身体を動かす姿から非認知的な能力を考える
幼稚園等の教育要領・小学校学習指導要領等では、「学びに向かう力」が重要といわれている。これは、ジェームズ・ヘックマンが教育経済学の立場から提唱した「非認知的な能力」であり、社会情動的スキルとも呼ばれているものである。ここでは、幼児(3歳児の12月)の身体を動かして遊ぶ場面から、そこで発揮されている非認知的な能力について考察していきたい。
事例(3歳児12月)
A児は、近くにあった段ボール積み木を鉄棒の下に持ってきて、その上に乗った。「先生、見てて」と言いながら両手で鉄棒を持ち、段ボール積み木の上でジャンプを繰り返していた。私(教師)は「わぁ、ポコポコ、何回もすごいジャンプだ」と応答する。A児と私のやりとりに誘われてか、B児は、並べて置いてある段ボール積み木の上を慎重に歩いて来た。端の積み木まで来ると、1mくらい離れているA児のいる鉄棒のところに向かって、膝を曲げてから両手を振り上げ身体全体を伸ばしながら思い切り跳んだ。
A児の隣に来たB児は、A児のする行為をたいへん短い時間ではあるが凝視して、同じように鉄棒を両手で持ちながらジャンプを繰り返す。
A児は積み木の端に足を着いたためバランスを崩して積み木が転がり、身体が勢いよく滑り落ちるように移動した。そして、積み木に座るような体勢でとまった。驚きと眩暈感覚的な快さが入り交じったような表情で一瞬動きが止まる。B児もこの様子を見ていて、A児の情動を一瞬にして受け取ったように、目を大きくして動きを止めながらも口元は緩んでいる表情を見せる。A児は同じ感覚が味わいたいようで、何度もジャンプして積み木に着地する足の位置を変えて試みるが、納得できない表情である。積み木の位置を後方にずらし、更に何度も繰り返していた。
A児やB児の様子を見ていた私の前をわざと横切るようにC児が走ってきた。私は「おおっ、C児くんが来た」と言う。C児は、並べて置いてある積み木の上を渡りジャンプして着地した。それをまねしてB児も同じようにした。次にC児は、積み木の上で片足跳びをした。B児はそれをじっと見ていた。B児は積み木の上に乗るが、片足跳びはせずに歩き、1m近くの大きなジャンプをして着地した。その後、地面で片足跳びを始めた。
10月以降、身体を思い切り動かして遊ぶ楽しさを味わうように、運動会で経験した遊びが実現できる遊具や新しい遊具を出すなど、園庭の環境の構成を工夫してきた。段ボール積み木や、保育室前に置いた移動式の鉄棒もその一例である。このような環境に関わって遊ぶ3人の幼児の姿をとらえた。
A児は、友達には関心をもちながらも自分から関わる姿は多くない幼児である。身体を動かす遊びは好きである。
B児は、入園当初は不安な気持ちと運動経験の不足から、自ら環境に関わって遊ぶ姿が見られず教師の後をついて過ごすことが多かった。幼稚園で様々な刺激を受けて、興味をもった友達や遊具、遊びに関わっていくようになってきた時期である。
C児は、自分のしたい遊びをのびのびと楽しみ、同じ場で一緒になった友達とも関わって遊んでいく幼児である。しかし、自分がしたいことが明確にあるので、ひとりで黙々と遊ぶ姿も多く見られる。身体を動かす遊びは好きで、多様な動きを体験している。
A児は、「飛び上がり」をするには高いと思ったのだろう、近くにあった段ボール積み木に乗ることを思いつき、すぐに鉄棒の下に持ってきた。段ボール積み木に上ってみると自分の体重で沈むことを感じてジャンプをしだしたのだろう。段ボール積み木の中身は空のペットボトルなので、ジャンプするたびに弾力性を感じていると思われる。教師に見てもらい認めてもらうことで得られる安心感や、ジャンプするたびに積み木の弾力を通して感じられる身体が揺れる心地よさなどを味わっている。
B児の慎重に積み木の上を歩く姿と、思い切り遠くへ跳ぼうとする姿には、内面の違いが感じられる。不慣れで不安定な段ボール積み木の上を落ちないように歩くということへの挑戦と、遠くに跳ぶ動きが洗練されていることから、今までに何度も体験しているであろう遠くまでジャンプするということへの自信である。B児がその後、目にしたA児の動きはB児を刺激し、興味・関心をもってまねをしたくなる対象になったと考えられる。B児は、よく見て(観察)、A児の動きの感じを運動メロディー(動き方や力の入れ方の連続的なまとまり)としてまるごと知覚し模倣している。
A児がバランスを崩したときに偶然感じた眩暈感覚のようなものと考えられる快さは、もう一度同じ感覚が味わいたくて何度も試す行為と意欲につながった。そして、A児の動きを至近距離で目の当たりにしたB児は、A児の一連の動きや表情からA児が味わった快さを受け取ったのだろう。だから、口元が緩んだ表情をしていたと考えられる。A児は何度も試す中で、積み木の位置をずらすということも行っている。
C児は、教師の前をわざと横切ってきたことから考えると、A児やB児を見守っている教師に自分の存在を知らせたいと思っていたのだろうと考えられる。だから、「ジャンプするから見ててね」「片足跳びもするから見ててね」という思いで遊び始めたのだろう。これは自己の存在意義を認めてもらいたいという思いであり、自己肯定感につながるものと考えられる。B児は、そのようなC児の動きにも興味をもち、よく見て(観察)、動きの感じをとらえて(運動共感)、模倣した。しかし、C児のように積み木の上では、片足跳びをしていない。すぐにまねをしないで、大きなジャンプをしている。これは、自信をもっているジャンプをすることで新しいことへ挑戦する気持ちを整えたのではないだろうか。
このような遊びが生まれた要因の一つに段ボール積み木の存在が考えられる。また、教師の存在も要因の一つだろう。教師に「見せたい」「認めてほしい」と幼児が感じるような信頼関係の構築と、幼児の行為を受容するように見守る教師の有り様が大切なのだろう。(中村 崇)
初出:つぽす(2018) 一部を改稿して掲載
ようかい体験
「ようかい体験」と聞くと、「ゲゲゲ」ですか?と思われるかもしれませんね。しかし、本稿で扱うのは「溶解体験」です。
現代の多くの人々は、有用性(役に立つか否か)を原理としての世界で生きているのではないでしょうか。しかし、それだけだと「今」の時間は未来の目的を実現させるための手段とみなされて、「今」はそれ自体では価値がなくなるように思われます。そこで溶解体験に着目したいと考えます。対象に見入ったり、聴き入ったりすることや心身で感じることを通して、自分と対象との境界が溶けたようになり、混然一体とすることを溶解体験と言います。「遊び込む」「没頭」「没入」「熱中」「ゾーンに入る」などと表現されることもあります。また「驚嘆」「畏敬の念」「センス・オブ・ワンダー」も溶解体験に深く関係するでしょう。溶解体験は、明確に意識して言語化することが困難な体験です。すなわち、既知の世界を破る認識不可能な「非知」の体験といえます。意味として定着できないからこそ、世界の新たな意味が生成されるのです。何かの役に立つことではなく、有用性にとらわれないことで可能になる心情の生成です。このような体験を深めるとき、不思議でおもしろく、魅力的で畏れるほど美しいこの世界と一体なのだという感覚が生成されるのでしょう。これは「自己の尊厳」を生み出す貴重な感覚なのです。
ここで私が担任をした3歳児A児の事例を紹介します。A児は、段ボール積み木(中に空のペットボトルが6本入っている段ボール箱)を鉄棒の下に持ってきて、その上に乗りました。両手で鉄棒を持ち、段ボール積み木の上でジャンプを繰り返していましたが、積み木の端に足を着いたためバランスを崩して積み木が転がり、身体が勢いよく滑り落ちるように移動し、積み木に座るような体勢になりました。驚きと眩暈感覚的な快さが入り交じったような表情で一瞬A児の動きが止まります。A児は同じ感覚が味わいたいようで、何度もジャンプして積み木に着地する足の位置を変えたり、積み木の位置をずらしたりしていました。何とも言えない「あの感覚」にまた出会おうと試みを繰り返していたのです。
私は保育者の皆様に、有用性としての経験のほかに、溶解体験にも着目して子供と一緒に遊ぶことを提案します。(中村 崇)
参考資料
矢野智司(1998)非知の体験としての身体運動~生成の教育人間学からの試論~.体育の科学.Vol.48.10月号
矢野智司(2006)意味が躍動する生とは何か―遊ぶ子どもの人間学.世織書房
川田 学(2019)保育的発達論のはじまり.ひとなる書房
初出:ぐんしよう №201 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
「だろう」「かもしれない」問題
30数年前の私は幼児教育専攻の学生で、教育実習での週案・日案作成に苦しめられていました。特に私を悩ませたのは、「予想される幼児の姿」の記述です。予想される姿ですから、文末は「~するだろう」「~するかもしれない」となります。「だろう」「だろう」ばかりが重なると読みにくいから、時には「かもしれない」と書いていました。とても未熟で、短絡的でした。
保育者になり、直感的・感覚的に書き分けるようにはなりましたが、ある日、中学校の教員に「指導案の『だろう・かもしれない』の違いはなに?」と聞かれ、明確に回答できませんでした。そこからやっと、「だろう」「かもしれない」問題に向き合う日々が始まったのです。保育者生活で掴んだ論理は次のとおりです。「だろう」と記述する予想される姿は、前週・前日の姿を基に、環境に関わって遊ぶ幼児の姿を推測したものです。逆に言えば、この「だろう」の姿が表れるような環境の構成を行うことが大切だと言えます。「かもしれない」と記述する姿は、もしかすると発展して表れるかもしれない姿を念頭に置いたものです。この「かもしれない」に対応する保育者の行為が「リソース(引き出し)」であり、「環境の再構成」として整理されることと考えます。しかし、時に「かもしれない」を超越する、予想が裏切られることが展開されます。困りますよね。いや、これこそが、「おもしろい」のです。佐伯1)は、保育者の何ごとも解釈してしまう心には「おもしろさ」は生まれず、むしろ「おもしろさ」が生じたときは「解釈」が吹き飛ぶと言っています。保育の、幼児の「おもしろさ」は、保育者の「かもしれない」を超えるところにあるのです。私たち保育者は、それを受け入れる度量を備え、「おもしろい」を感じたいですね。(中村 崇)
1)「ビデオによるリフレクション入門 実践の多義早発性を拓く」佐伯胖・刑部育子・苅宿俊文2018東京大学出版会
初出:ぐんしよう №200 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 本稿は、一部改稿したもの
ジャンケンで決める
「ジャンケンでしか決めらんないん?(決められないの?)」
「ほんとにそれでいいんかい?(本当にそれでいいの?)」
これは私が幼稚園で担任をしていたとき、“もめ事”の際に幼児に掛けた言葉です。幼児が自分たちで“もめ事”の解決を図ろうとしているのだから、なぜそのようなことを言うのかなあ、自分たちで生活していこうとする素晴らしい姿ではないか、などと御批判もありそうです。
「ジャンケン」は、ロジェ・カイヨワの言う「アレア(運や賭けを伴う遊び)」であり、偶然性の内に面白さがあります。「あっち向いてホイ」にはなくてはならないものですし、「かくれんぼ」「鬼ごっこ」の鬼を決める際にもたいへん有効な手段です。サッカーのゲーム前のコイントスのように、異議を言う者はいないと思います。
“もめ事”は、幼児の日常の中にあります。意見の食い違い、役割の決定、ものの取り合い、順番・・・等、これを「ジャンケン」で決めることが、平和的で協働的な社会の実現を目指す未来の担い手としての子供たちに積極的に経験してほしいことなのかと、私は自身に問い続けています。
大学に勤務していた恩師と上述のような「ジャンケン」にまつわる私の実践と課題意識について話をしているなかで、次のように伺ったことがあります。「学生は、研究室・ゼミでの役割などをジャンケンで決めようとする。一緒に過ごす仲間であるからこそ、互いの特性やサポートの体制、挑戦する意欲等を念頭に、ジャンケンではない方法を探ってほしいと、その都度提案してきたが・・・」という話です。それぞれが背負っている背景や、そこに至る文脈を受けて進んでいく効率的ではない人間社会の意味について再考するきっかけになったことを記憶しています。
もう20年も前になりますが、小学校の生活科の授業を参観したことがあります。グループで考えたゲーム(この授業では「遊び」と言っていたが、敢えて「ゲーム」と表現する。その意図は、前回の「ぽんぽこコラム」を参照)を紹介する授業でした。「タイヤのある場所」をめぐって二つのグループによる「どちらが先に使うか」についての“もめ事”が起こりました。近くにいた先生は「ジャンケンしなさい」と言ったのです。子供たちが、自他の思いや状況に気付き、なんとか前に進むために折り合いをつけたり、アイデアを出し合ったりする貴重な学びの時が失われた瞬間でした。
次に幼稚園で体験したエピソードを記します。5歳児のAちゃんとBちゃんは、同じ図柄のチラシで紙飛行機を作り園庭で飛ばしていました。一つの紙飛行機が水溜まりに着陸し泥で汚れました。Aちゃんは近くに着陸した汚れていない紙飛行機を自分のものだと言います。Bちゃんはびっくりした表情でAちゃんが主張する汚れていない紙飛行機が自分が飛ばしたものだと言います。二人の会話は言い争いに発展しました。私はそこに2時間ほど関わることになりました。私が留意したことは二つです。一つは、時間が長くなるとBちゃんが諦めて、「もういいよ」と言って去ろうとするのを引き留めること。もう一つは、このままだと互いに相手は自分のことをどのように思って今後の友達関係を続けることになるのだろう?という問い掛けを様々なアプローチで伝えること。最終的には2時間後、Aちゃんは、泥で汚れたのが自分の紙飛行機であることを話し、私も含めてみんな自然に涙があふれ出し、三人で肩を抱き合いました。
ジャンケンに委ねるのではなく、大人が決めるのでもなく、子供が自分で、自分たちで、「どうにか」する。子供と共に悩みながら、この過程の中で何が経験され、何が育ちゆくのかを理解していくことが大事なのではないかと思うのです。子供が「どうにか」しようと対象に向かっていく状況づくりは、子供が自分自身の世界を広げようとすることにつながり、それこそが質の高い教育なのではないかと、「ジャンケン」を通して思いをめぐらせた話です。(中村 崇)
初出:ぐんま幼児教育センターだより 第44号
「遊び」-「遊ぶ」をめぐる教師の視点と“構え”
みなさんは、子供の「遊び」をどのように捉えていますか。仲間と一緒に笑顔で活動していることを、「遊び」をしていると捉えますか。この「遊びをしている」と「遊ぶ」に違いはあるのでしょうか。本稿は、子供の育ちを支える教師の指導の在り方について、「遊び」-「遊ぶ」をめぐる教師の視点と“構え”という視座から考えていきたいと思います。
「遊び」については、ヨハン・ホイジンガの「ホモ・ルーデンス」やロジェ・カイヨワの「遊びと人間」をはじめ、様々な考察が行われてきました。私が本稿で取り上げるのは、杉原隆の論考です。杉原は「生涯スポーツの心理学」(2011)にて、内発的に動機づけられた活動こそが「遊び」であるとし、「遊び」を連続体として捉えることを提言しています。人間は、一つの動機だけで活動することは少ないと考えられますので、遊びを内発的動機かそうでないか(外発的動機)という二分法で捉えることは困難であるわけです。そこで、内発的動機づけを「遊び要素」、外発的動機づけを「非遊び要素」と考え、内発的動機づけが強いほど遊び的な活動であり、逆に外発的動機づけが強くなるほど遊びではなくなるとしたのです。例えば、友達と一緒にやりたい(親和動機)、先生に褒められたい(承認動機)、その活動の面白さに惹かれている(内発的動機)などのように同時に複数の動機をもっている場合、友達と一緒にやりたいとか先生に褒められたいとの思いが強い場合は非遊び要素が高く、その活動の魅力や面白さに惹き付けられている場合は遊び要素が高いということになります。このように、同じ活動をしていても、遊びとしての活動という場合もあれば、まったく遊びとは言えない活動もあることになるわけです。このような「遊び」の捉えを見ていくと、私たち教師は前述の意味での「遊び」の発生を支え、時間的・空間的・人的な保障をしていくことがその役割と考えられます。
しかし、子供と共に過ごす中で意識を向ける必要があるのは、むしろ「遊ぶ」ではないのかという考えにも至るのです。「遊ぶ」という行為の中で子供は何を経験し、何が育ちつつあるのかを読み取って、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を念頭に置きつつ、子供理解に基づく一人一人の発達の課題に子供自身が向かっていく(乗り越えていく)状況をつくることが、本質的な教育の意味(教師の役割)と考えるのです。この教育実践には、幼児期の教育に携わる教師(保育者)の高度なファシリテーションスキルが有効に働いていると考えられます。ファシリテーションスキルには、基本的な四つのスキル「場をデザインするスキル」「対人関係のスキル」「構造化のスキル」「合意形成のスキル」があると言われます。「場をデザインするスキル」は、「環境の構成」という考え方、特に「状況づくり」が深く関係しています。「対人関係のスキル」は、安心感や信頼関係、そして「構造化のスキル」「合意形成のスキル」は子供と一緒に悩むという姿勢、すなわち子供の主体性や思考を促す“構え”に深く関係しています。
このような教師の視点と“構え”は、今日的な教育課題である「STEAM教育」や「非認知能力(社会情動的スキル)の育成」等を乗り越えるヒントにもなり得ると考えられます。幼児教育施設に所属の皆様は、「〇〇遊び」という“かたち”ではなく、「遊ぶ」という行為に内在する教育的価値に一層深く意識を向けてみてはいかがでしょうか。小・中・高・特別支援学校に所属の皆様は、幼児期の教育の理解を進めてみてはいかがでしょうか。(中村 崇)
初出:ぐんま幼児教育センターだより 第41号
次回が楽しみになる園内研修
みなさんは、園内研修についてどのようなイメージをもっていますか?ある報告によると「お腹が痛くなる」「自分の意見に反論されたらどうしよう」などが挙げられていました。そこで今回は、「次回が楽しみになる園内研修」について考えていきたいと思います。
まず、確認しておきたいのは、園内研修を行う目的です。園の置かれてる状況により様々な目的が考えられますが、大きな目的は質の高い保育の実現と言えるのではないでしょうか。質の高い保育とは、幼児の視点から見ると自由感あふれる保育であり、保育者側から見ると幼児の遊びの中に教育的価値を見いだし、その幼児の発達の課題に幼児自身が向かっていく状況をつくることだ言えます。質の高い保育を支えるのは、幼児理解です。人間は思い込みで目の前の現象を見ていると言われます。「思い込み」を外さないと幼児理解は深まりません。そこに有効に働くのが「園内研修」だと考えられます。多様な視点に触れ、各保育者が自身の幼児理解に揺らぐ体験をすることで「思い込み」を外すのです。
それでは保育カンファレンスを例に、「次回が楽しみになる園内研修」を探りましょう。保育カンファレンスが有効に機能するためには、「話の具体性」「発言の対等性」が必要です。「話の具体性」を実現するために、従来は事例を活用してきました。そのよさについては申し上げるまでもありませんが、逆に事例の準備に負担感を抱く場合もあります。そこで、写真を活用してみてはいかがでしょうか。写真とそれにまつわる話を提供することで具体性を実現していきます。また、「発言の対等性」が保障されるためには、管理職やベテラン保育者が導くという「伝達型」からの脱却が必要です。そこで、管理職等はファシリテーターや板書役を担い、各保育者のよさが発揮される状況づくりを行います。このような環境が整った上で、建前でなく本音で話すことを推奨していきます。保育上の問題意識について保育者自身の内面をさらけ出す必要があるからです。そして、相手を批判したり優劣を競おうとしたりしないで、相手の意見が間違っていると感じた場合でも、それをよい方向に向けて建設的に生かす方向を大事にします。ポジティブな発言を多くすることです。そして、「正解」を求めようとしないで、多様な意見が出されることを目指し、まとまらなくても時間で終わりにすることが重要です。つまり、多様な視点に触れ、自分の視点に揺らぐことに意味があるからです。
おわりに、最近体験した私の揺らぐ体験について記します。ある園を参観させていただいたときの話です。友達の上履きを履いて嬉しそうな表情で歩くAちゃんがいました。その後、違う友達のものも履いていました。私は、その上履きの持ち主のことが好きなのだなと理解しました。数日後、ラジオから「誰かの靴を履いてみること」の話題が聞こえてきました。それは、「エンパシー(共感・感情移入)」についての解釈だったのです。私はドキッとして、記録用に撮っていた映像を見返しました。Aちゃんが履いていた上履きの持ち主の二人とも、先生の膝に腰掛け絵本を読んでもらっていたのです。もしかして、Aちゃんはこの二人の上履きを履くことで、先生の膝で絵本を聞く情況を味わっていたのかもしれません。 (中村 崇)
初出:ぐんしよう №189 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会