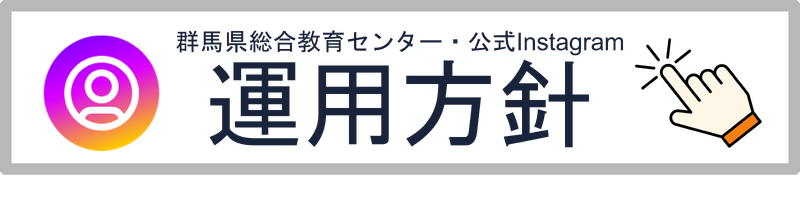|
〒372-0031 |
ようかい体験
「ようかい体験」と聞くと、「ゲゲゲ」ですか?と思われるかもしれませんね。しかし、本稿で扱うのは「溶解体験」です。
現代の多くの人々は、有用性(役に立つか否か)を原理としての世界で生きているのではないでしょうか。しかし、それだけだと「今」の時間は未来の目的を実現させるための手段とみなされて、「今」はそれ自体では価値がなくなるように思われます。そこで溶解体験に着目したいと考えます。対象に見入ったり、聴き入ったりすることや心身で感じることを通して、自分と対象との境界が溶けたようになり、混然一体とすることを溶解体験と言います。「遊び込む」「没頭」「没入」「熱中」「ゾーンに入る」などと表現されることもあります。また「驚嘆」「畏敬の念」「センス・オブ・ワンダー」も溶解体験に深く関係するでしょう。溶解体験は、明確に意識して言語化することが困難な体験です。すなわち、既知の世界を破る認識不可能な「非知」の体験といえます。意味として定着できないからこそ、世界の新たな意味が生成されるのです。何かの役に立つことではなく、有用性にとらわれないことで可能になる心情の生成です。このような体験を深めるとき、不思議でおもしろく、魅力的で畏れるほど美しいこの世界と一体なのだという感覚が生成されるのでしょう。これは「自己の尊厳」を生み出す貴重な感覚なのです。
ここで私が担任をした3歳児A児の事例を紹介します。A児は、段ボール積み木(中に空のペットボトルが6本入っている段ボール箱)を鉄棒の下に持ってきて、その上に乗りました。両手で鉄棒を持ち、段ボール積み木の上でジャンプを繰り返していましたが、積み木の端に足を着いたためバランスを崩して積み木が転がり、身体が勢いよく滑り落ちるように移動し、積み木に座るような体勢になりました。驚きと眩暈感覚的な快さが入り交じったような表情で一瞬A児の動きが止まります。A児は同じ感覚が味わいたいようで、何度もジャンプして積み木に着地する足の位置を変えたり、積み木の位置をずらしたりしていました。何とも言えない「あの感覚」にまた出会おうと試みを繰り返していたのです。
私は保育者の皆様に、有用性としての経験のほかに、溶解体験にも着目して子供と一緒に遊ぶことを提案します。(中村 崇)
参考資料
矢野智司(1998)非知の体験としての身体運動~生成の教育人間学からの試論~.体育の科学.Vol.48.10月号
矢野智司(2006)意味が躍動する生とは何か―遊ぶ子どもの人間学.世織書房
川田 学(2019)保育的発達論のはじまり.ひとなる書房
初出:ぐんしよう №201 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会