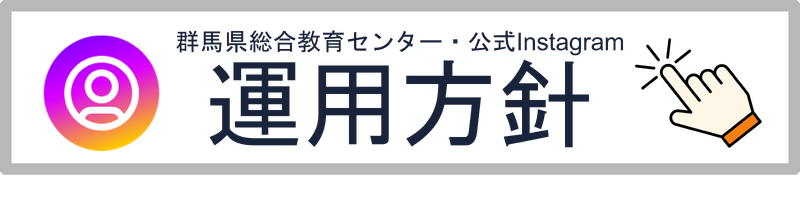|
〒372-0031 |
「だろう」「かもしれない」問題
30数年前の私は幼児教育専攻の学生で、教育実習での週案・日案作成に苦しめられていました。特に私を悩ませたのは、「予想される幼児の姿」の記述です。予想される姿ですから、文末は「~するだろう」「~するかもしれない」となります。「だろう」「だろう」ばかりが重なると読みにくいから、時には「かもしれない」と書いていました。とても未熟で、短絡的でした。
保育者になり、直感的・感覚的に書き分けるようにはなりましたが、ある日、中学校の教員に「指導案の『だろう・かもしれない』の違いはなに?」と聞かれ、明確に回答できませんでした。そこからやっと、「だろう」「かもしれない」問題に向き合う日々が始まったのです。保育者生活で掴んだ論理は次のとおりです。「だろう」と記述する予想される姿は、前週・前日の姿を基に、環境に関わって遊ぶ幼児の姿を推測したものです。逆に言えば、この「だろう」の姿が表れるような環境の構成を行うことが大切だと言えます。「かもしれない」と記述する姿は、もしかすると発展して表れるかもしれない姿を念頭に置いたものです。この「かもしれない」に対応する保育者の行為が「リソース(引き出し)」であり、「環境の再構成」として整理されることと考えます。しかし、時に「かもしれない」を超越する、予想が裏切られることが展開されます。困りますよね。いや、これこそが、「おもしろい」のです。佐伯1)は、保育者の何ごとも解釈してしまう心には「おもしろさ」は生まれず、むしろ「おもしろさ」が生じたときは「解釈」が吹き飛ぶと言っています。保育の、幼児の「おもしろさ」は、保育者の「かもしれない」を超えるところにあるのです。私たち保育者は、それを受け入れる度量を備え、「おもしろい」を感じたいですね。(中村 崇)
1)「ビデオによるリフレクション入門 実践の多義早発性を拓く」佐伯胖・刑部育子・苅宿俊文2018東京大学出版会
初出:ぐんしよう №200 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会 本稿は、一部改稿したもの