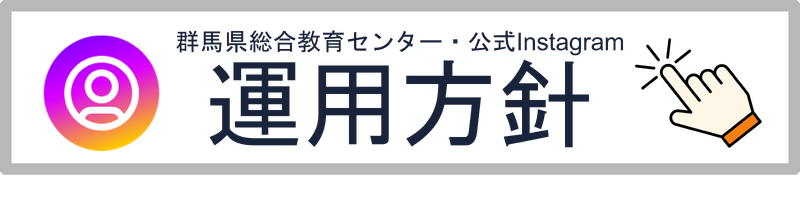|
〒372-0031 |
「環境の構成」と「方法としての教師」
「環境の構成」とは、子供が興味・関心のある環境に働き掛けて遊ぶことで、(子供本人は期せずして結果的にもしくは近い将来に)自身の発達の課題を自分で乗り越えるための意味のある状況づくりをする教師の営みであると私は解釈しています。すなわち、ものを配置するだけにとどまらず、時間や雰囲気等が相互に関連し、周囲の人(友達・教師など)との関係性の中で環境が意味(教育的価値)をもつことに教師は意識を向ける必要があるということです。さらに、遊びの展開により環境は再構成され、常に動的な遊びを支える役割も忘れてはなりません。教師が望んでいる活動を引き出すための材料や用具を用意し、幼児の活動を誘発する“コーナー保育”に代表される「環境構成」とは明らかに違うものなのです。子供がエージェンシーを発揮し、自らの世界を広げていくためには、「環境の構成」の考え方が必要になってきます。
環境の構成が有効に機能するためには、教師の在り方が重要になってくると考えます。我々幼児教育センターでは、子供が環境を通して自ら主体的に学んでいくために欠かせない存在である教師を「方法としての教師」1)2)と呼ぶことにしました。「方法としての教師」とは、子供がねらいに向かうための手立てとしての教師の在り方であり、教育の手段としての教師の存在とも言えます。いくら物的環境を整えても、それらと子供を結びつける意図的な教師の動きが不可欠であり、具体的には「子供の活動の意味を理解する」「子供の目線に立つ」「思いに共感し共鳴する」「学ぶ姿や関わる姿のモデルになる」「必要な人に対して必要なときに必要な援助を行う」「子供が精神的に安定するためのよりどころ」などの役割が重要であると考えます。このような教師の存在により子供は、「安心」と「自由感」を得て主体性を発揮していくでしょう。
かねてより研修等でお伝えしてきたことですが、「○○遊び」をさせることが重要なのではなく、子供がどのようなことをして遊んでいても、その中に教師が教育的価値を見いだすことが重要なのです。これが環境を通して行う教育であり、遊びを通した総合的な学びなのです。
「環境の構成」は、小学校以降の教育でも有効に働くと考えます。(中村 崇)
1)中村 崇(2016)幼児の運動発達を促す教師の役割.群馬大学教育実践研究 第33号 pp.227-235
2)大島 崇・中村 崇・太田紀子(2025)子供に内在する非認知能力の発揮及び伸長を促す架け橋期の教育.群馬県総合教育センター
参考資料:森上史朗・柏女霊峰編(2011)保育用語辞典[第6版].ミネルヴァ書房:京都.
初出:ぐんしよう №202 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
一部を改稿して掲載