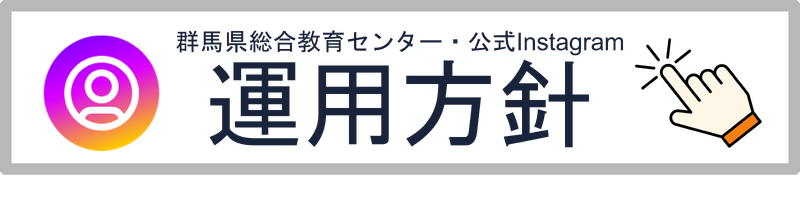|
〒372-0031 |
幼児の身体を動かす姿から非認知的な能力を考える
幼稚園等の教育要領・小学校学習指導要領等では、「学びに向かう力」が重要といわれている。これは、ジェームズ・ヘックマンが教育経済学の立場から提唱した「非認知的な能力」であり、社会情動的スキルとも呼ばれているものである。ここでは、幼児(3歳児の12月)の身体を動かして遊ぶ場面から、そこで発揮されている非認知的な能力について考察していきたい。
事例(3歳児12月)
A児は、近くにあった段ボール積み木を鉄棒の下に持ってきて、その上に乗った。「先生、見てて」と言いながら両手で鉄棒を持ち、段ボール積み木の上でジャンプを繰り返していた。私(教師)は「わぁ、ポコポコ、何回もすごいジャンプだ」と応答する。A児と私のやりとりに誘われてか、B児は、並べて置いてある段ボール積み木の上を慎重に歩いて来た。端の積み木まで来ると、1mくらい離れているA児のいる鉄棒のところに向かって、膝を曲げてから両手を振り上げ身体全体を伸ばしながら思い切り跳んだ。
A児の隣に来たB児は、A児のする行為をたいへん短い時間ではあるが凝視して、同じように鉄棒を両手で持ちながらジャンプを繰り返す。
A児は積み木の端に足を着いたためバランスを崩して積み木が転がり、身体が勢いよく滑り落ちるように移動した。そして、積み木に座るような体勢でとまった。驚きと眩暈感覚的な快さが入り交じったような表情で一瞬動きが止まる。B児もこの様子を見ていて、A児の情動を一瞬にして受け取ったように、目を大きくして動きを止めながらも口元は緩んでいる表情を見せる。A児は同じ感覚が味わいたいようで、何度もジャンプして積み木に着地する足の位置を変えて試みるが、納得できない表情である。積み木の位置を後方にずらし、更に何度も繰り返していた。
A児やB児の様子を見ていた私の前をわざと横切るようにC児が走ってきた。私は「おおっ、C児くんが来た」と言う。C児は、並べて置いてある積み木の上を渡りジャンプして着地した。それをまねしてB児も同じようにした。次にC児は、積み木の上で片足跳びをした。B児はそれをじっと見ていた。B児は積み木の上に乗るが、片足跳びはせずに歩き、1m近くの大きなジャンプをして着地した。その後、地面で片足跳びを始めた。
10月以降、身体を思い切り動かして遊ぶ楽しさを味わうように、運動会で経験した遊びが実現できる遊具や新しい遊具を出すなど、園庭の環境の構成を工夫してきた。段ボール積み木や、保育室前に置いた移動式の鉄棒もその一例である。このような環境に関わって遊ぶ3人の幼児の姿をとらえた。
A児は、友達には関心をもちながらも自分から関わる姿は多くない幼児である。身体を動かす遊びは好きである。
B児は、入園当初は不安な気持ちと運動経験の不足から、自ら環境に関わって遊ぶ姿が見られず教師の後をついて過ごすことが多かった。幼稚園で様々な刺激を受けて、興味をもった友達や遊具、遊びに関わっていくようになってきた時期である。
C児は、自分のしたい遊びをのびのびと楽しみ、同じ場で一緒になった友達とも関わって遊んでいく幼児である。しかし、自分がしたいことが明確にあるので、ひとりで黙々と遊ぶ姿も多く見られる。身体を動かす遊びは好きで、多様な動きを体験している。
A児は、「飛び上がり」をするには高いと思ったのだろう、近くにあった段ボール積み木に乗ることを思いつき、すぐに鉄棒の下に持ってきた。段ボール積み木に上ってみると自分の体重で沈むことを感じてジャンプをしだしたのだろう。段ボール積み木の中身は空のペットボトルなので、ジャンプするたびに弾力性を感じていると思われる。教師に見てもらい認めてもらうことで得られる安心感や、ジャンプするたびに積み木の弾力を通して感じられる身体が揺れる心地よさなどを味わっている。
B児の慎重に積み木の上を歩く姿と、思い切り遠くへ跳ぼうとする姿には、内面の違いが感じられる。不慣れで不安定な段ボール積み木の上を落ちないように歩くということへの挑戦と、遠くに跳ぶ動きが洗練されていることから、今までに何度も体験しているであろう遠くまでジャンプするということへの自信である。B児がその後、目にしたA児の動きはB児を刺激し、興味・関心をもってまねをしたくなる対象になったと考えられる。B児は、よく見て(観察)、A児の動きの感じを運動メロディー(動き方や力の入れ方の連続的なまとまり)としてまるごと知覚し模倣している。
A児がバランスを崩したときに偶然感じた眩暈感覚のようなものと考えられる快さは、もう一度同じ感覚が味わいたくて何度も試す行為と意欲につながった。そして、A児の動きを至近距離で目の当たりにしたB児は、A児の一連の動きや表情からA児が味わった快さを受け取ったのだろう。だから、口元が緩んだ表情をしていたと考えられる。A児は何度も試す中で、積み木の位置をずらすということも行っている。
C児は、教師の前をわざと横切ってきたことから考えると、A児やB児を見守っている教師に自分の存在を知らせたいと思っていたのだろうと考えられる。だから、「ジャンプするから見ててね」「片足跳びもするから見ててね」という思いで遊び始めたのだろう。これは自己の存在意義を認めてもらいたいという思いであり、自己肯定感につながるものと考えられる。B児は、そのようなC児の動きにも興味をもち、よく見て(観察)、動きの感じをとらえて(運動共感)、模倣した。しかし、C児のように積み木の上では、片足跳びをしていない。すぐにまねをしないで、大きなジャンプをしている。これは、自信をもっているジャンプをすることで新しいことへ挑戦する気持ちを整えたのではないだろうか。
このような遊びが生まれた要因の一つに段ボール積み木の存在が考えられる。また、教師の存在も要因の一つだろう。教師に「見せたい」「認めてほしい」と幼児が感じるような信頼関係の構築と、幼児の行為を受容するように見守る教師の有り様が大切なのだろう。(中村 崇)
初出:つぽす(2018) 一部を改稿して掲載