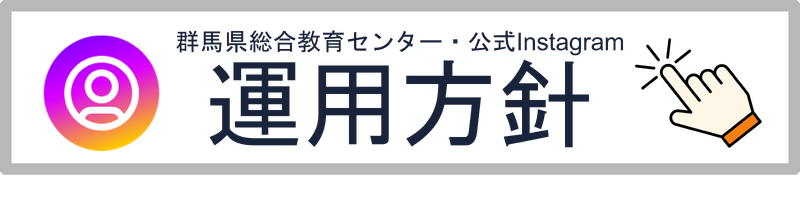|
〒372-0031 |
ジャンケンで決める
「ジャンケンでしか決めらんないん?(決められないの?)」
「ほんとにそれでいいんかい?(本当にそれでいいの?)」
これは私が幼稚園で担任をしていたとき、“もめ事”の際に幼児に掛けた言葉です。幼児が自分たちで“もめ事”の解決を図ろうとしているのだから、なぜそのようなことを言うのかなあ、自分たちで生活していこうとする素晴らしい姿ではないか、などと御批判もありそうです。
「ジャンケン」は、ロジェ・カイヨワの言う「アレア(運や賭けを伴う遊び)」であり、偶然性の内に面白さがあります。「あっち向いてホイ」にはなくてはならないものですし、「かくれんぼ」「鬼ごっこ」の鬼を決める際にもたいへん有効な手段です。サッカーのゲーム前のコイントスのように、異議を言う者はいないと思います。
“もめ事”は、幼児の日常の中にあります。意見の食い違い、役割の決定、ものの取り合い、順番・・・等、これを「ジャンケン」で決めることが、平和的で協働的な社会の実現を目指す未来の担い手としての子供たちに積極的に経験してほしいことなのかと、私は自身に問い続けています。
大学に勤務していた恩師と上述のような「ジャンケン」にまつわる私の実践と課題意識について話をしているなかで、次のように伺ったことがあります。「学生は、研究室・ゼミでの役割などをジャンケンで決めようとする。一緒に過ごす仲間であるからこそ、互いの特性やサポートの体制、挑戦する意欲等を念頭に、ジャンケンではない方法を探ってほしいと、その都度提案してきたが・・・」という話です。それぞれが背負っている背景や、そこに至る文脈を受けて進んでいく効率的ではない人間社会の意味について再考するきっかけになったことを記憶しています。
もう20年も前になりますが、小学校の生活科の授業を参観したことがあります。グループで考えたゲーム(この授業では「遊び」と言っていたが、敢えて「ゲーム」と表現する。その意図は、前回の「ぽんぽこコラム」を参照)を紹介する授業でした。「タイヤのある場所」をめぐって二つのグループによる「どちらが先に使うか」についての“もめ事”が起こりました。近くにいた先生は「ジャンケンしなさい」と言ったのです。子供たちが、自他の思いや状況に気付き、なんとか前に進むために折り合いをつけたり、アイデアを出し合ったりする貴重な学びの時が失われた瞬間でした。
次に幼稚園で体験したエピソードを記します。5歳児のAちゃんとBちゃんは、同じ図柄のチラシで紙飛行機を作り園庭で飛ばしていました。一つの紙飛行機が水溜まりに着陸し泥で汚れました。Aちゃんは近くに着陸した汚れていない紙飛行機を自分のものだと言います。Bちゃんはびっくりした表情でAちゃんが主張する汚れていない紙飛行機が自分が飛ばしたものだと言います。二人の会話は言い争いに発展しました。私はそこに2時間ほど関わることになりました。私が留意したことは二つです。一つは、時間が長くなるとBちゃんが諦めて、「もういいよ」と言って去ろうとするのを引き留めること。もう一つは、このままだと互いに相手は自分のことをどのように思って今後の友達関係を続けることになるのだろう?という問い掛けを様々なアプローチで伝えること。最終的には2時間後、Aちゃんは、泥で汚れたのが自分の紙飛行機であることを話し、私も含めてみんな自然に涙があふれ出し、三人で肩を抱き合いました。
ジャンケンに委ねるのではなく、大人が決めるのでもなく、子供が自分で、自分たちで、「どうにか」する。子供と共に悩みながら、この過程の中で何が経験され、何が育ちゆくのかを理解していくことが大事なのではないかと思うのです。子供が「どうにか」しようと対象に向かっていく状況づくりは、子供が自分自身の世界を広げようとすることにつながり、それこそが質の高い教育なのではないかと、「ジャンケン」を通して思いをめぐらせた話です。(中村 崇)
初出:ぐんま幼児教育センターだより 第44号