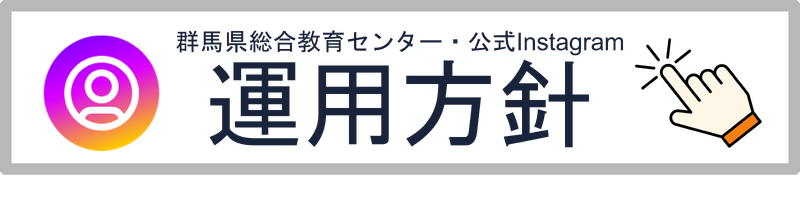|
〒372-0031 |
せん長の「ぽんぽこコラム」
てんぷら
葉っぱのてんぷらレシピを記します。
これは、以前お世話になった保育者の方から教えていただいたものです。
材 料:新鮮な葉(雑草の大きめな葉)・水・おがくず
作り方:①葉を水につけて、濡らします。
②濡らした葉におがくずをまぶします。
③皿に盛りつけます。
園におがくずは常時ないですよね。子供たちと一緒に遊ぶ中で、おがくずの代わりに使ってみたものは、栗の花や枯れた葉をすり鉢で細かくしたものです。
子供たちと「代替食材」を探すのもおもしろいでしょうね。(中村 崇)
「の」の ひみつ
Googleマップを見ていたら、?!!「の」があるではないですか。おもしろい、なんだろう、という思いに駆られ調べてみました。あるお宅の庭にある道でした。この心が躍る体験は、貴重な「溶解体験」(以前このコラムに書きました)になりました。
今回は、「の」のひみつを探っていきたいと思います。なんの「の」かと言いますと、「発達段階」と「発達の段階」、「発達課題」と「発達の課題」、「環境構成」と「環境の構成」の「の」です。「の」が付くか否かで、それぞれが表す文言に違いはあるのでしょうか。
「の」が付くときは、例えば「環境」と「構成」を分けて捉えてほしいときなのだと考えます。すなわち、「発達段階」、「発達課題」、「環境構成」が従来もっている意味とは違う意味を表現したいのだろうと考えます。
「発達段階」とは、多くの人に共通して見られる発達の道筋であると言われています。一方、「発達の段階」とは、人生という道の過程での変容としての「発達」における、その人またはその人たちの今の位置という意味での「段階」と考えられます。
「発達課題」とは、人間が健全で幸福な発達をとげるために各発達段階で達成しておかなければならない課題であり、次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題があると言われています。一方、「発達の課題」とは、「発達」という人の生きる過程の中で、その人が乗り越えることで新しい世界が開ける意味での「課題」と考えられます。
「環境構成」とは、保育者が望んでいる遊びや活動を引き出すための材料や用具を用意し子供の活動を誘発するという考え方を基にした物的環境を準備・配置することと言われています。一方、「環境の構成」とは、子供の興味・関心に即した「環境」(もの、人、自然・社会現象、時間、空間、雰囲気など)を相互に関連させながら、その子供にとって必要な体験を積み重ねていける状況づくりを「構成」と捉え理解することができます。
「の」のひみつを探る話はこれでおしまいです。様々な考え方はありますが、私なりの考えをまとめてみました。この思考過程は、私にとっておもしろくて刺激的な体験でした。(中村 崇)
Googleマップは、Google LLCの商標です。
初出:ぐんしよう №203 (一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会
ところでさぁ
幼稚園で担任をしていたときの話です。
Aちゃんが、おうちの方の仕事について、自分が知っている情報を情熱的に伝えています。
A:「印刷の仕事はねえ、大きな機械を動かしてね、すごいたいへんなんだよ」
私:「そうなんだぁ。たいへんな仕事なんだね」
A:「そうなんだよ」
Aちゃんの動きが一瞬止まり、そして私の顔をじっと見つめて
A:「ところでさぁ、せんせいって、何の仕事してるん?」
私:「えっ?‼」(今度は私の動きが止まった)
保育者として、Aちゃんからもらった最高の言葉だったと思います。なぜなら、毎日、真剣に子供たちと遊んでいたことを認められたと思うからです。Aちゃんは、この「せんせい」という大人は毎日、自分たちと遊んでいて仕事をしているのかなあ、不思議だなあ、と思ったのではないでしょうか。
子供の言葉を大人の視座で理解(理解力の不足など)するなら、子供の心に寄り添う教育の実現は難しいと考えます。そして子供の姿は、保育者の保育についての評価であると考えます。子供の評価のみで、保育者自身の評価が外れていることはないでしょうか。(中村 崇)
ゴム跳び?
ある園の園内研修に伺いました。幼児の運動発達について、実技を交えながらの研修です。私は先生方に問い掛けます。「子供のころ、ゴム跳び、したことありますか?」
「あります。あります」(少数派)
「えー?ないです」(多数派)
あります、ありますの二人の先生にお手伝いいただいて、私がまずはやってみます。地域ごとにやり方は様々だと思うので、「○○町で生まれ育った、○○歳の私が子供のときにやったのは」と言いながら、「グー・パー・グー・踏み・グー・パー・ねじって・ピョン・A・B・C」と跳んでみます。
「おー‼」(拍手)と先生方が盛り上げてくれます。
続いて、あります、ありますの先生がノリよく、「○○市の○○歳がやりまーす」と言って、私とはちょっと違ったやり方を見せてくれました。
「おー‼」(拍手)と先生方が笑顔になります。
少数派は保育経験を重ねた先生方で、多数派はこれから保育者としての経験を積み重ねていこうとする先生方でした。このように自分の子供時代に遊んだことなどを実際の動きとともに伝え合う機会は、相互理解を促し、同僚性を高めることにつながるでしょう。
また、自身の幼少期の記憶をたどってみると、子供にとって遊ぶこととは何かについて、じっくり考えるきっかけになるのではないでしょうか。(中村 崇)
駄菓子屋のおばちゃん方式
子供のころ、「おぎんちゃんち」という駄菓子屋さんに仲間と一緒によく集まっていました。店主のおぎんちゃんは、子供たちをよく理解していたように思います。今で言うインフルエンサー的な子に、「今度、学校でビー玉、流行らせておくれ」と言って、ビー玉が数個入っている袋を無償(ただ)で渡すのです。ビー玉をもらったその子は、仲間にビー玉で遊ぼうと誘い、瞬く間にビー玉が流行り、「おぎんちゃんち」の売り上げは伸びることになります。
私は教師・保育者になってから、この現象を思い出し、人の行動変容に係る環境(人的なものを含める)の重要さに気付いたのでした。それ以降、私はこれを「駄菓子屋のおばちゃん方式」と呼んでいます。(中村 崇)